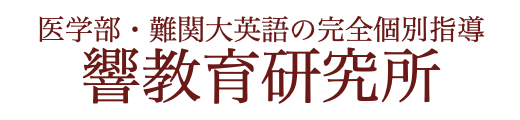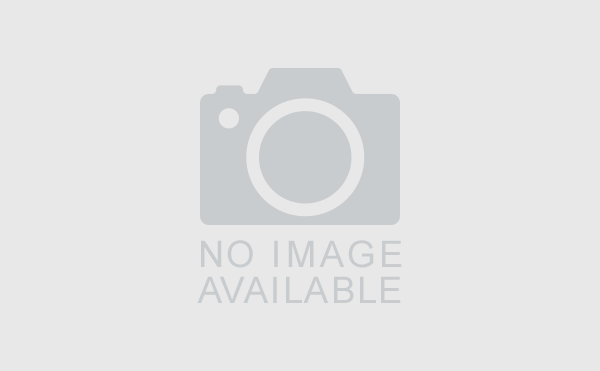苦手意識(思い込み)の払拭②
たいていの苦手意識はいつの間にかできてしまうものですが、かなりはっきりと原因がわかっているものもあります。早すぎる過去問演習です。一部の進学校で見られるのですが、高1で旧帝大などの過去問を授業で扱うのです。先生方としては、難しいレベルに触れさせて発奮させたいとか、あるいは、もう解けるはずだと思っているのか、目的は色々でしょうが、ほとんどの生徒にとっては、早すぎるのです。
ある受験生が、受ける可能性があるというので、旧帝大の〇〇大の過去問を解いてみるように言ったところ、
「はい……。」と浮かないお顔。「〇〇大の和訳は難しいから、できるかなぁ。訳語の決め方が特殊ですよねえ」
はて? 私はあらかじめその英文をざっと読んでいました。もちろん難関大レベルではありますが、内容も取りやすく、訳語が特殊ということもない。しかも、その生徒さんは英語が得意で、もっと難しい文も含めて普段から和訳演習をしているのです。
おかしいぞと思ってよく話を聞いてみると、学校で高一の時に〇〇大過去問の和訳をやって、「すごく難しかった」のだそう。その印象が深く刻まれてしまったのですね。そりゃあ、1年生では難しいでしょう。要らぬ「苦手意識」が作られたものです。
そこで、その場で一つ和訳に取り組んでもらうことにしました。初見の文を目の前で1回音読のうえ、5分くらいで訳してもらいます。出来上がった訳は十分よくできています。
「どう? 難しかった?」
「いや、フツーです」
「だよね。いつももっと難しいのできてるもんね。高一の時には、難しかったってだけだよ」
苦手だという思い込みを作ってしまうくらいなら、早すぎる過去問演習は有害です。学校には、高2までは基礎に抜けを作らないことをしっかりやってほしいものです。