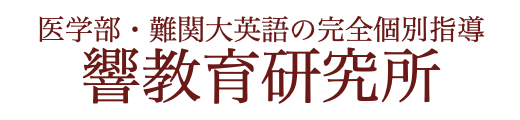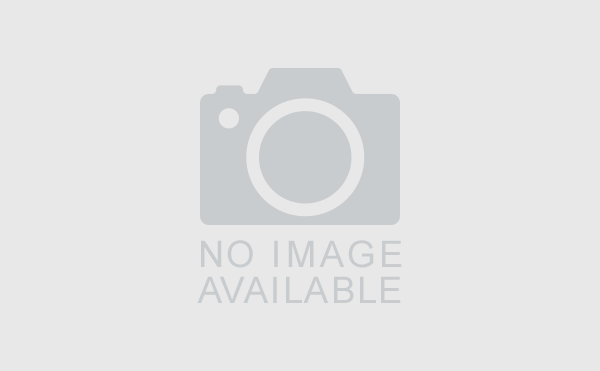「学校の古文が嫌い」
先日、ある高校一年生から、学校の古文がつまらないしわからないという話を聞きました。ずっとやっている敬語と文法が難しいのだそうです。
小テストを見せてくれたのですが、一行にも満たない一節(一文ですらない)が何十個も羅列されていて、傍線部の助動詞の意味・活用形やら、単語の訳やらを答えていく、初級の古文問題集などによくあるタイプの設問です。
初級だからこそ、一節だけ抜き出しの設問になるのでしょうが、初級だからこそ、これはつまらない。前後のつながりも、何の話かも全くわからない一節を次から次へと読んで、文法解読していく。しかも単語訳の採点もとても厳しくて、「かわいい」なら正解だが、「かわいらしい」では不正解。いや、どっちでもいいじゃん。
細かいところがわからなかろうが、とにかくストーリーのあるお話をどんどん読んでいけば良いのです。文法は読解を助けるために役に立つに過ぎないのだから、肝心の文章を読むことをおろそかにして文法ばかりやらせるのは本末転倒です。それも、”理解”よりも”暗記”の方向なので、よくわからないまま反復テストをさせられて、古文が嫌いになってしまう。なんてもったいない!
その高校生も、今までの私の生徒さんたちと同様に、「漢文は面白い」と言います。漢文は書き下しても古文にしかならないのに、それを面白く読めるということは、文法はそこそこでも古文が読めて楽しめるほどの能力がすでにあるということです。なんてすばらしい!
単語や文法知識は、正確に読むためにはもちろん不可欠です。でもまずは短いお話や、なじみのあるお話、王朝文化を楽しめるお話をどんどん読んでいけばよいのです。その中で重要な単語はかなり覚えてしまいますし、慣れてきたら文法を加えていけば、抵抗なく知識が入っていきます。その結果手にするものは、テストの点数という次元のものにとどまらない、教養です。