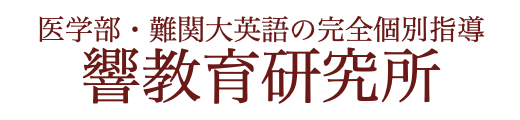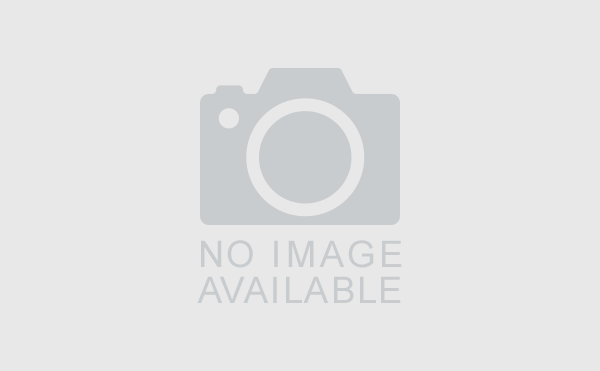英語「リスニングが苦手」を分解する①
リスニングは大学によって試験がある所とない所があり、あっても配点が少なかったり、東大のように馬鹿にならない量があったりします。そのため対策もしにくく、つい後回しになってしまいますね。練習しようにも音源は東大や共通テストの過去問くらいで、適切な教材を見つけるのも一苦労です。だからといって放置しておくのも不安。ではどうしたらよいのでしょうか。
ひと口に「リスニングが苦手」と言っても、実はそこにはさまざまな要素があります。自分の苦手要素がどれなのかをまずは分析してみましょう。
知らない単語や表現があって話がわからなくなってしまう
毎回わからない単語が出てくるような場合は、まず単純に単語力・基礎力不足です。耳で聞いたせいでわからないのではなく、綴りを見てもそもそも知らない単語が多すぎるのです。語彙力を強化するのであれば、耳だけに頼ったリスニング演習を繰り返すよりも、目も手も口も耳も使って通常の勉強をした方がずっと効率的です。
一方、数は多くないけれども知らない単語があると気を取られてしまい、続きを聞き逃してしまうという人もいます。この場合は、おそらく長文問題でも、知らない単語に遭遇するとたちまち混乱してしまう可能性が高いです。推測力・読解力不足です。外国語なのですからたまに知らない単語があるのは当たり前。前後の話から推測したり、部分的に迷子になってもまた途中から復帰すればよいのです。これも、どんどん音が流れていってしまうリスニング演習で対策するよりも、まずは何度でも読み返すことのできる長文で、推測や復帰の訓練をする方がやりやすく、当然長文読解力も上がるので、一石二鳥です。
続きはまた次回に。🤗