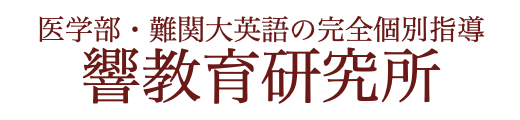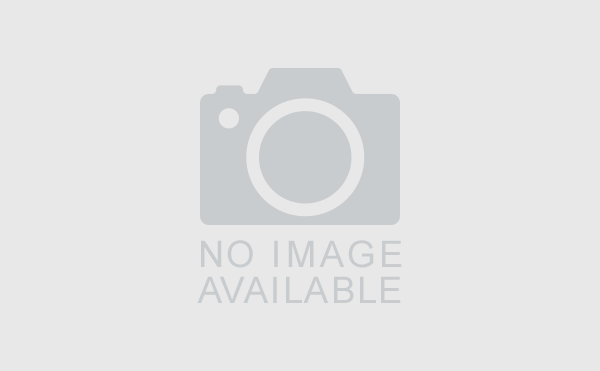英語「リスニングが苦手」を分解する③
のべつまくなしに聞き取って、何の話かわからなくなる
「さあ、聞き取るぞ!👂」と気合を入れれば入れるほど、肩に力が入ってしまうものです。耳をそば立てて一語一語漏らさずに聞き取れるのはよいとして、しばらく続くうちに、初めの方の内容は忘れてしまって、一体何の話がどう進んだのかわからなくなってしまうことがあります。
実はこれも長文読解でもありうることで、典型的な「木を見て森を見ず」の状態に陥っているのです。文章には緩急があって、内容の濃い重要な部分と、情報の少ないあっさりした部分が混在しているものです。それをどれも同じ気合いで読んでしまうと、重要な部分がどこだかわからなくなり、話の流れ(文脈)も見失いやすくなります。
実際のリスニングでは設問の下読みをする段階で、何の話題でどんなキーワードが出てくるのかはあらかじめわかるので、放送が始まったあとは大体の流れをざっくり掴もうというくらいのリラックスした気持ちでいる方が、下読みした大切な部分が目立って聞こえてくるので、かえって全体の内容を理解しやすくなるのです。
文章には緩急があるということ、一文の中にすら強く読まれる大事な単語とそうでない単語があり、段落にすら重要なものとほぼ読み飛ばしても構わないくらいの薄いものがあるということは、ある程度勉強して英語が読めるようになってきた人に意識してほしいポイントです。音読の仕方も変わってくるはずです。長文演習でそれがわかってくると、リスニングでも同じなので、気合を入れすぎることなく聴くことができるようになってきます。
そうは言っても、肩の力を抜いて聴くには慣れも必要ですから、直前期に、あるいは模試を利用してちょくちょくと、練習するくらいはしておくと安心できると思います。