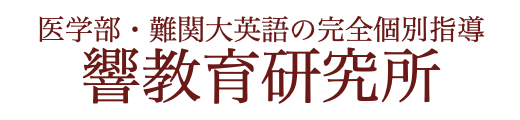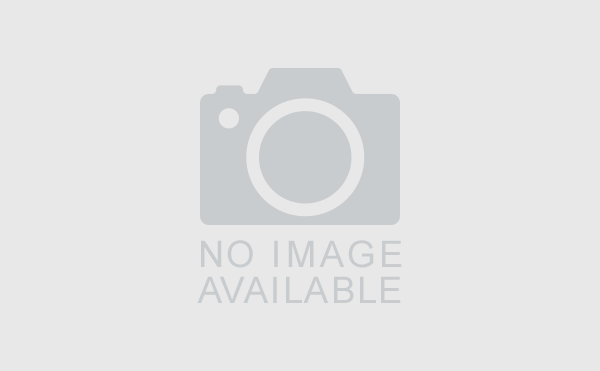英語「リスニングが苦手」を分解する④
久しぶりのブログ更新です。先週は風邪をひいてずっとグズグズしていました。その間に駿台の全国模試がありましたね。リスニングはどうでしたか?
下読みに時間がかかる。読んでも忘れてしまう
リスニングでよくあるお悩みに、下読みに時間がかかりすぎるというものがあります。耳だけで聞き取る自信はないので、あらかじめできるだけ詳しく内容を知っておきたいし、聴きながら選択肢を読むのは無理があるので、設問すみずみまで全部読んでおかないと不安。というわけで、音声開始前の下読みに10分近くかけてしまう。その場合、さすがにリスニングではかなり得点できるのですが、他のリーディングの問題に割ける時間が少なくなって、そちらでの失点につながってしまう。リスニングが長い場合や問題数が多い場合には、せっかく細かく読んでも内容を忘れてしまうということもあります。(私は結構コレです。😅)
まず、下読みの時間を短縮するには、ここでもやはり「速読即解力」(『英語「リスニングが苦手」を分解する②』を参照)を訓練する必要があります。一読して理解できるのと、「えっと、主語はこれで、分詞がここにかかっているから……」とゆっくり考えないとつかめないのとでは、設問文を1〜2行と1行の選択肢を4つ読むうちに、馬鹿にならない時間差が生まれます。
そして、せっかくつかんだ内容を忘れないようにするには、丸で囲んだり、線を引いたりして、設問のポイントや選択肢同士の「違い」を目立たせておきます。漢字仮名混じりの日本語を使っている我々には、小さなアルファベットだけが連なった英文では、視覚的にメリハリが感じられません。ですから、書き込みによって「見て分かる」状態にしておくのです。「要するに」何を聞かれていて、各選択肢の答えが「要するに」何なのかという最重要部分のみを目立たせておくのです。
そしてここでも、その「要するに」というポイントをつかむ力は、リスニング固有の技能ではありません。和訳でも長文でももちろん要約でも(さらに言えば日本語の文章であっても)、常に「何の話?」、「要するにどういうこと?」と頭を働かせながら読む(聴く)ことこそが「読解」の基本です。普段の長文読解演習においても、また国語をやっている方は国語の読解においても、読みながら同時に書き込みをする練習を続けてみてください。