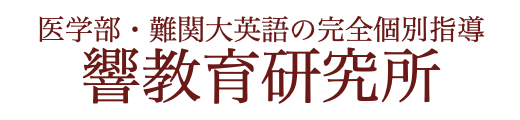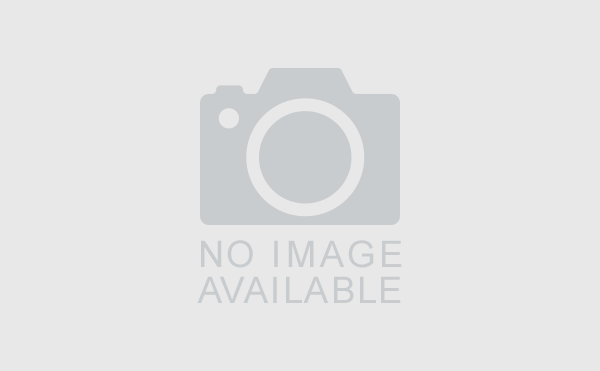教え方の変化①
30年近く授業をしてきて、最近(といっても、5年以上前?😅)敢えてやらなくなったことがあります。それは、「転ぶ前にこっそり道を整える」ことです。黒子型の教え方とでも言いましょうか。
一人一人の生徒さんとじっくり向き合っていると、その方がこの先どのポイントでつまづきそうかがわかります。その前に先回りして、必要なことをさりげなく繰り返したり、少し迂回して順番を変えたりして、生徒さん本人は全く気がつかないまま難所をあっさりと通過できるようにします。
以前はこのような教え方ができるようになったことを誇りに思っていたものです。今でも全くやらないわけではなく、一例を挙げれば、「学校で古文が始まる。どうしよう、きっと難しい」と始まる前から苦手意識を持ってしまっている中学生に、雑談に出てきた好きなマンガや旅行で行った(行ってみたい)名所を挙げて、「あなたの好きな◯◯が出てくるよ。マンガみたいなかっこいいセリフとかたくさん出てくるから、きっとあなたには面白いと思うよ」という具合に少し暗示をかけるように言うだけで、淀んでいた目がキラキラとしてきます。偏見や自分はダメだという思い込みを消すことで、順調なスタートを切ることができます。
この例は、新科目のスタートという大きな話ですが、英文法や古文・漢文のあらゆる学習過程に小さな難所が散らばっているものです。それらを難なく通過して行けばいつの間にか英語も古典も相当なレベルになるはずですね。
では、なぜその方法を取らなくなったかというと、一言で言えば、「予後が悪い」からです。