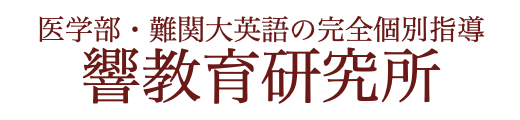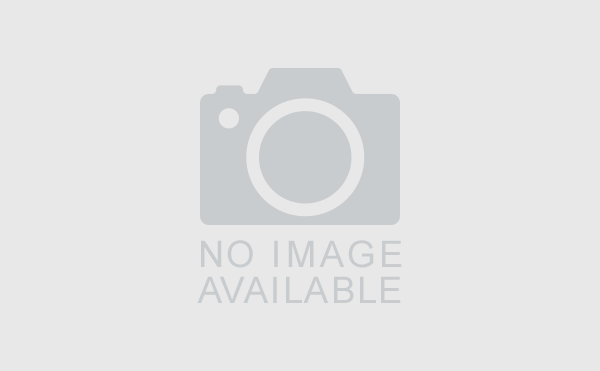教え方の変化②
(前回の続きです。『教え方の変化①』)「予後が悪い」結果となった例を挙げてみます。
高校1年生で中2英語まで遡って基礎のやり直しをしていた方が、次週の定期テスト範囲を教えてくれたので、主に中2の教材を使いながらも、「これは学校のテストにも出るよ」と、テスト範囲の重要表現や、その時点でも理解しやすい文法内容を混ぜて授業をしました。次回の授業でもさらに繰り返しや続きを加えればテストも大丈夫と考えていたところが、「テスト直前なので」という理由で前日になって授業をキャンセルされてしまいました。同じ理由で授業を増やしてほしいというご希望はよくあるのですが、逆だったので驚きましたが、これは学校のテストにも役立つことをしているという自覚が生徒さん側になかったからです。
その結果、テスト結果は思わしいものではありませんでした。学校とは別に着々と進んでいた中2の復習も、「こんなのやっても意味がない」と考えたようで、中途半端になっていき、まもなく指導終了ということになりました。当時、出講していた塾の生徒さんでしたので、講師交代となったのですが、その後の大学受験も塾への朗報はありませんでした。
ここまで極端ではなくても、転ぶ前にこちらが道を整える方法ばかりだと、あまりにもスムーズに進みすぎて、生徒さんの方には挫折感もない代わりに、「ここまで来た」という達成感もありません。過保護すぎて、今自分に何ができて、何ができないかを意識する必要がなく、「今やっていることは普通にやってたら普通にできた。受験ではもっと難しいのができるようにならなきゃいけないのに。」と物足りなさを感じるようです。
一方で、必要なフォローは行いながらも、ちょっとした困難にぶつかった場合に、その行き詰まった自覚を持った生徒さんに対して、すでに持っている知識をもとに解決のヒント(ヒントだけ)を出して、しばらく頑張ってもらうと、その時は多少の時間がかかっても、乗り越えた時には「わかったー! もう大丈夫」と自信を持ち、先へ進もうとします。「予後が良い」のです。
過保護な黒子型も、自力克服援助型も、加減の問題や、個人の違いはもちろんあります。子育て論とも重なりますね。よく「二人三脚で受験を乗り切る」などの表現がありますが、大学受験ともなると「自立」を促すことが正しい方法であるように思います。