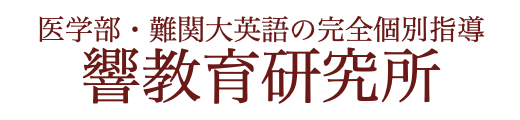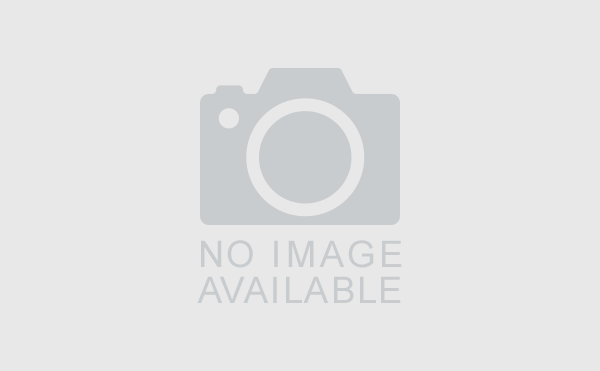中学入学時点で英語力が二極化?
引き続き、小学校での英語教育についてです。英語が教科化された後の生徒たちが中学生になりました。先日読んだある記事では、中1の時点で実力分布がフタコブラクダ化しているということでした。テストの点や偏差値ごとに何人の生徒がいるかをグラフ化していくと、模試のデータでもお馴染みの分布図が出来上がります。普通は上と下(左と右)が細く、真ん中(平均)が太いヒトコブラクダ状のグラフになります。単純に実力差が大きいというだけなら、緩やかで長いヒトコブになるだけです。その記事によれば、下のコブは、小学校で英語が嫌いになってしまい、授業についていけない層だということでした。
昨日までのブログにも書いている通り、私自身は、もし小学校で英語の授業を受けていたら大混乱していただろうと思うので、ついそちらの層に感情移入してしまいます。歌や遊びから楽しく英語に触れましょうというスタンスの授業であっても、「恥ずかしくって教室で歌なんて歌えないよ」という私のようなタイプの人は、英語の時間自体が苦痛だっただろうなぁ〜。😫 算数や国語など他の教科と同じように、初めからお勉強として教わった方がいいなぁ〜。
人によって実力差があるのも、好き嫌いがあるのも、それ自体は当然で仕方のないことだと思いますが、理念も準備もない付け焼き刃の「改革」の結果は、目指したはずの日本人全体の英語力の強化を、むしろ早い段階で困難にしているようです。