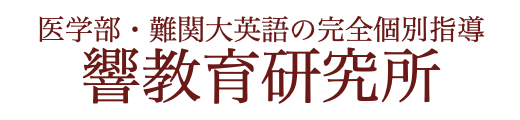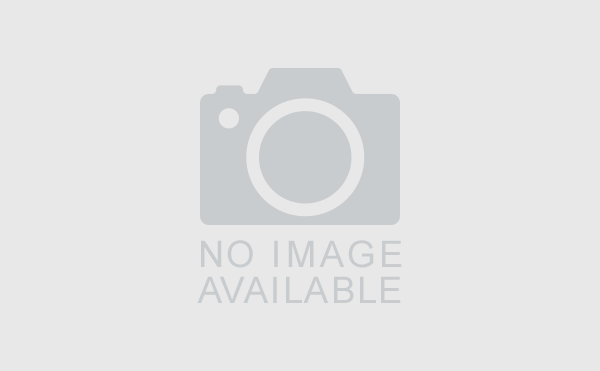英語の長文、読んでから解く? 読みながら解く?
模試などの長文問題で、「ちゃんと読めるけど、時間が足りなくなる」というご相談を受けることがあります。見ると、前半の問題は記述も含めてとても良くできているのに、後ろの方の設問でポロポロ落としたり空欄があったりと、明らかに時間がなくなってしまった形跡があります。解き方を詳しく聞くと、「一旦最後まで通して読んでから、問1から順番に解いていく」とのこと。
外国語で1〜2ページにもわたって長々と何か書いてあるのですから、とりあえず読み通して全体を把握したいと思うのは当然のことです。その上で、何を聞かれているかに注意しながらもう一度細かく読めば、内容もより深く頭に入ってきます。ですが、この当然で自然な読み方をしていると、試験では時間がなくなるのですね。特に近年は短時間で大量に読ませる試験が増えているので尚更です。逆に言うと、出題側がそこまで丁寧な読み方を求めていない、さらに言うと、一読してわかる程度の出題しかしていないということです。そういうことなら解答者側もその程度の読み方をしていけばいいのです。一番極端な例を挙げるなら、今年1月の共通テスト英語リーディングです。読み返しをしている時間はありません。ほとんどの私大医学部の英語も同じです。
一旦最後まで読みたいタイプの人にとっては少しストレスのかかる練習になると思いますが、読む文章に合わせて読み方は変わる(変える)ものですから、別の読み方も身につけるつもりで練習してみましょう。その際、少し易しめの長文を使った方が良いです。文章を読みながら、ある程度のところで区切ってそこまでの設問を解き、またある程度読み進めたらそこまでの設問を解き、文章を読み終えるとほぼ同時に設問も解き終わっているようにするのです。初めにどんな設問なのかをみておくのも良いでしょう。