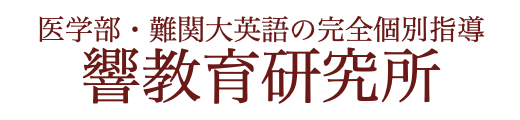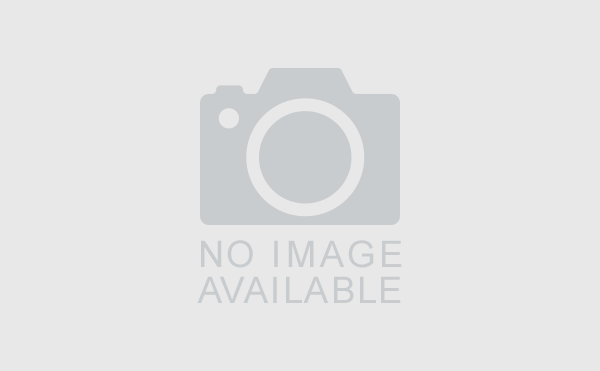ローマ字なのかアルファベットなのか
私が今の小学生だったらきっと英語が苦手になっていただろうなと思う理由の一つは、「ローマ字」です。昔は小学校4年でローマ字を習いました。その時点で英単語の綴りなど全く知らないので、「日本語のローマ字表記」として習います。平仮名、片仮名の延長みたいな意識です。「か」は「ka」、「き」は「ki」というように、むしろ日本語の50音の仕組みがはっきりと視覚化されます。同時に「k、s、t、n、h、m、y、r、w」の9つの子音字のおおよその発音が頭に入るので、のちに英単語を学習したときに、ローマ字読みによってある程度の発音を知ることができました。
当時のクラスメイトに、公文ですでに高校数学をやっているようなものすごく優秀な人がいました。その友人は「つ」を「tu」ではなく「tsu」と書き、「し」を「si」ではなく「shi」と書いていて、「ヘボン式っていうんだよ」と教えてくれましたが、私には、なぜ「た行」に「s」が入り、「さ行」に「h」が入るのか、さっぱりわかりませんでした。しまいには「tsu」が「stu」だか「tus」だか混乱する始末。ヘボン式表記が理解できるようになったのは、中学で英語が始まり、「cat」の複数形は「cats」とか、「sea」と「she」の発音の違いなどをさんざん習ってからでした。
今は小学校3年生でローマ字を学習します。同時に英語も始まります。読んだり書いたりするのは5年生からのようですが、教科書には当然英単語が載っています。「フルーツ」がなぜ「furutu」(2こめのUの上に棒線)ではないのか、「fruit」なら「フルイト」ではないかと、ローマ字による日本語表記と、アルファベットによる英語表記に、当時の私なら大混乱です。それならむしろ日本語のローマ字表記を教えない方がいいような気がしますが、自分の名前をローマ字で書けないのも困ります。ううーーーむ。