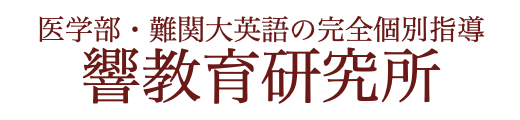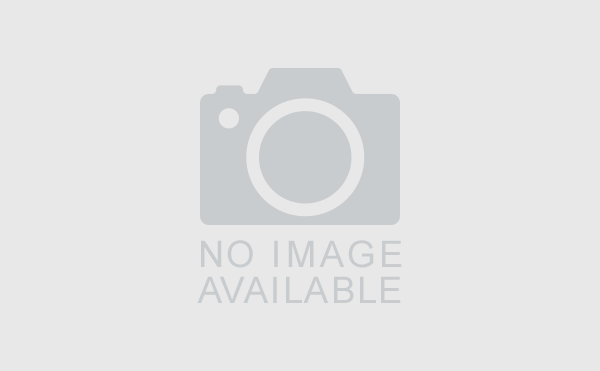「あんなに勉強したのに英語が話せない」って本当?
学校での英語教育の早期化は、国会のおじさん(おじいさん?)たちの英語コンプレックスに一因があると思います。もちろん社会の側にも、「あんなに勉強したのに全然喋れない。大学受験の小難しい読解だの文法だの無意味じゃないか」という共通認識があるようです。でも、「それって本当?」と大いに疑問に思います。
かく言う私自身も、かつては全く同じように感じていました。大学生になってイギリスに行った時に、英語が聞き取れない、言いたいことがうまく伝えられない、発音すら通じないことがあると言う事実に落ち込みました。そして6年以上も真面目に勉強してきたのに、こんなに英語が喋れないのだったら教育の仕方が間違っているのだと思いました。
今では単純に英語を話す機会が少なすぎただけだったと思っています。今の学校では私の頃よりスピーキングを訓練される機会は多いと思いますが、教室の授業だけではタカが知れていますし、学校外で英語を話さなければならない場面もほぼありません。訓練していなければ、できないのは当たり前です。
外国語の場合、「読む、書く、聴く、話す」の四つのうちで、一番高度なのは「話す」です。発音も、語彙力も、ある程度の文法力も、瞬発力も、そして何よりも度胸が必要だからです。「聴く」と「話す」の訓練がかつての学校教育に足りなかったのは確かで、改善していければ良いのですが、それは「読む」と「書く」の訓練だけでも大変な時間がかかるという事情があります。話せないからといって「読む・書く」を飛び越えて「話す」訓練だけをすることは不可能だと思います。