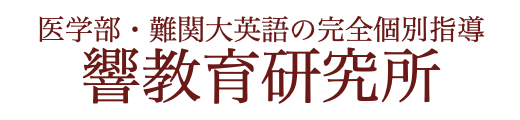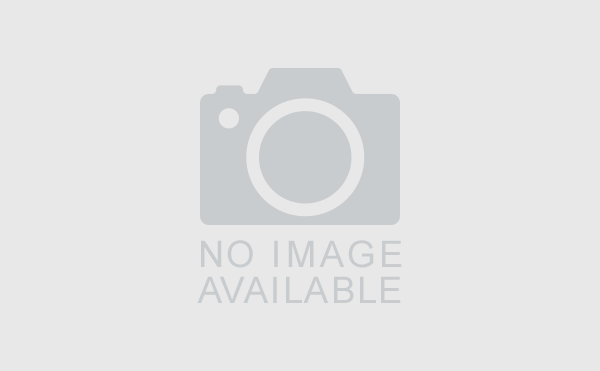苦手意識(思い込み)の払拭①
「あれ? わかんない」という問題にぶつかったときに、
「ほらね、やっぱり難しい問題が出た」と思うか、
「そんなはずはない。落ち着いて、ちゃんと読もう」と思うかで、
正答できるかどうかは大きく変わってきます。前者のように「思ってしまう」根本には、勉強中にいつの間にか形成されてきた『苦手意識』、あるいは『思い込み』があります。個別指導では、生徒さんとのふとした会話がこの苦手意識の発見と解決につながることがとても多いです。
ある私大医学受験生が過去問に取り組んでいた時、
「ああ、これだ! この大学は毎年一問、超難しい問題が出るから……。」
と呟きました。
おやおや? そんなはずはないけど。こちらも毎年解いているので知っていますが、その医大の英語はやや特色はあるものの、設問のレベルは平易で、大部分を占める選択式問題は、英語が得意な人ならほとんど正解できるくらいです。ミスや読み間違いは起こるとしても、必ず一問難問があるなどということは決してありません。
そこで、一問一問確認しながら一緒に見ていきました。すると、引っ掛かっていたのは、図表や地図などを組み合わせた大問の最後の設問でした。普通の長文なら、始めから終わりまで順に読んでいけばどこかに答えのもとが書いてあるのにぶつかりますが、図表やチラシなどの資料も併記してある場合は見つけにくくなります。でも、表のタイトルや、図のはじに書かれた注意書きなどに、ポロッと必要な情報が書かれています。あると思って探せば、「あった、これか!」と見つけて済んでしまう非常に単純な問題でした。本文の内容が読めているのによくわからない設問があった場合は、本文以外の部分を落ち着いて探せば良いだけだったのです。
このことで、「必ず一問難しい」という思い込みは払拭できたようで、その生徒さんはまさにその大学に合格しました。めでたし、めでたし。😊